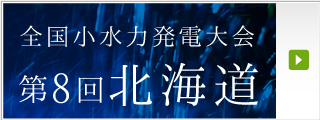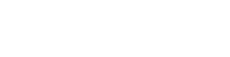山形市の松原浄水場に小水力発電施設が整備され、完成式が2日、同市小白川町5丁目の現地で行われた。同浄水場で使用する全ての電力量を賄うことができるほか、24時間発電のため、災害などによる停電時も浄水が可能となった。
敷地東側に、地上1階地下1階の鉄筋コンクリート製の建物(延べ床面積約180平方メートル)を設けた。発電設備は、主水源の蔵王ダムから同浄水場まで の高低差と導水管を流れる水を利用しており、年間発電電力量は約70万キロワット時。市制施行125周年事業として約3億3500万円で整備し、このうち 約2億4600万円は県の市町村防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業の補助を受けた。
来年度以降は、新たに不動沢を水源とする水も利用できるようにし、水量を増加させることで同浄水場の年間電力使用量にほぼ相当する約100万キロワット時を発電できるようにする。一般家庭約290世帯分の使用量に当たるという。
発電による電力は、同浄水場で活用。発電電力量が増える来年度以降の経費削減効果を約1170万円と見込む。余剰電力は東北電力に売る。同社は今月から 再生可能エネルギーの電力の買い取り契約手続きを一部中断しているが、市は「契約は(中断前の)8月に交わしており、変更はない」としている。
完成式には関係者約60人が出席し、市川昭男市長ら代表者7人でテープカットを行った後、発電機が起動した施設内を見学した。