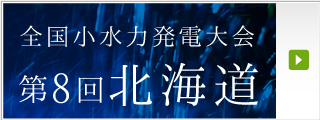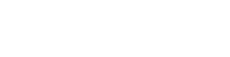福島県の南西部に位置する下郷町に建設された小水力発電所「花の郷発電所」が商業運転を開始した。発電出力は175kW(キロワット)で、年間の発電量は一般家庭で約300世帯分となる約100万kWh(キロワット時)だ。[長町基,スマートジャパン]
丸紅の100%子会社である三峰川(みぶがわ)電力は、2015年2月に完成した福島県下郷町の小水力発電所「花の郷発電所」(図1)の商業運転 を同年6月18日に開始した。同発電所は下郷町中山地区の準用河川大沢川より取水して、山間部の落差を利用して発電を行う。発電出力は175kW(キロ ワット)で、年間の発電量は一般家庭で約300世帯分となる約100万kWh(キロワット時)だ。発電した電力は再生可能エネルギーの固定価格買取制度を 活用して東北電力に売電する。
 図1 福島県下郷町の「花の郷発電所」出典:丸紅
図1 福島県下郷町の「花の郷発電所」出典:丸紅三峰川電力は下郷町と「下郷町における再生可能エネルギー開発に関する基本協定書」を締結している。今後も同町内の複数地点において小水力発電所 開発を進め、メンテナンスの効率化などのシナジー効果を創出していく。さらに今後も小水力発電をはじめ同町の潜在資源を利用した発電事業を展開し、下郷町 が目指す自然エネルギーを活用する未来のまちづくりに貢献していく方針だ。
豪雪地帯の福島県南西部に位置する下郷町は、会津若松市に接している。人口は約6000人で、町内には重要伝統的建造物群保存地区の「大内宿」な どがある。小水力発電事業は大規模なダム建設と比較して環境負荷が低く、地域にある農業水路などの遊休落差を利用できるなどのメリットもあり、今後電源の 多様化が進む中で有用な電源の1つとして期待されている。
丸紅は2006年から小水力発電の運営を行っており、三峰川(長野県伊那市)、蓼科(同茅野市)でそれぞれ2カ所、北杜(山梨県北杜市)で3カ 所、さらに今回の花の郷発電所を加えて国内で8カ所の小水力発電所が商業運転を開始している。同社は今後、2020年までに国内で累計30カ所程度の中・ 小水力発電所の開発を目指す方針だ。
http://www.niigata-nippo.co.jp/life/tourist/news/20150623188855.html